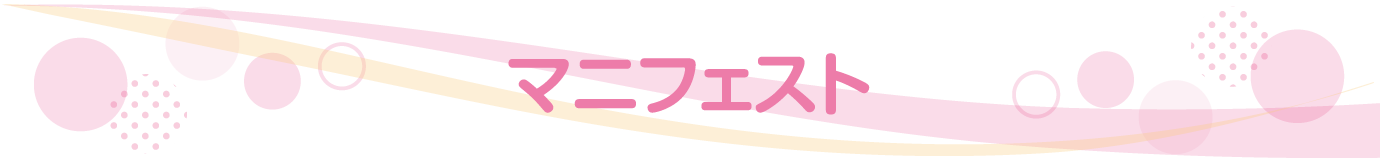私は22年前に夫の実家のある芦屋町に移り住みました。子育てをしながら介護ヘルパーやケアマネジャーとして働き、町民の皆様や福祉の現場の声を町政に届けたい一心で町議会議員となり、この約7年間活動してまいりました。その間、改善されたこともありましたが、人口減少や少子高齢化など、まだまだ課題は山積しています。
私はこれからも芦屋町をもっと安心して暮らせるまち、これからも住み続けたいまちにしていきたいと考え、10年先、20年先の将来を見据えたまちづくりに取り組みたいと考えています。
はぎわらの4つの政策
「対話と住民参画でもっと
暮らしやすいまちへ」
Action 01
対話・住民参画による協働のまちへ
- 町民の皆さまが本当に困っていることを一緒に解決できるよう対話の機会を設けます。
★定期的に自治区などを訪問し、町民の皆さまとの対話を重ね、一緒に今後のまちづくりを考えていきます。
自治区や地域コミュニティの推進に特化した担当部署を創設します。
★芦屋町の自治区加入率は低下傾向にあり、町の大きな課題の1つです。地域コミュニティをしっかり作ることは、災害対策や地域住民の幸福度を左右する重要な要素(良好な近所づきあいや友人、家族とのつながりなど)と考え、新たな担当部署を創ります。
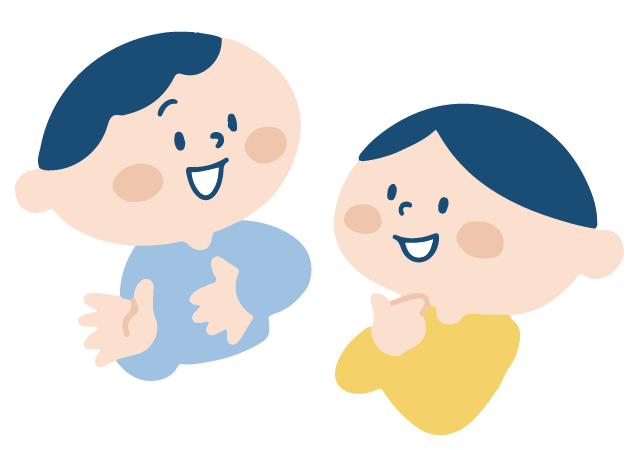
Action 02
安全安心なまちへ
- 雨水排水対策や下水道の耐震化などの災害対策に取り組みます。
★今年の8月の三連休、線状降水帯による集中豪雨で町内でも浸水被害が発生しました。近年、大規模地震や線状降水帯による大雨により、各地で甚大な被害をもたらしています。そのため、雨水排水や下水道の耐震化などの災害対策に取り組みます。
- より実践的な避難訓練を計画するとともにペット同伴の避難訓練も実施します。
★現在、年2回の避難訓練を実施していますが、さらに実践的な訓練を計画します。また「ペットがいるので避難所に行けない」といった声を聞きます。誰もが安心して避難できるようペット同伴の避難訓練も行います。

Action 03
もっと子育てしやすいまちへ
- 給食費を含む保育料の完全無償化を進めます。
- 小中学校の学力向上に取り組みます。
- 高校生の就学支援金支給(2万円/月)、大学生の生活支援を行います。
★芦屋町の課題である人口減少対策の1つとして、子育て支援に力を入れます。そのために、給食費を含む保育料の完全無償化やさらに小中学生の学力を向上に取り組みます。また、子育て世帯における高校や大学の教育費は大きな負担となることから、新たに高校生等の就学支援金の支給を行うとともに、経済的負担の大きい大学生への支援策も速やかに打ち出し、人口増加戦略につなげます。

Action 04
産業・観光・文化の力で元気なまちへ
- 町の賑わいや町民の健康増進を目的に温泉掘削を検討します。
★「老人憩の家」の廃止が決定しましたが、高齢者にとっての憩の場、集える場は絶対に必要です。ただ、今後の少子高齢化も見据えると、高齢者だけではなく、みんなが集える場を作りたいと考えています。
また、芦屋港レジャー港化で計画していた「砂像屋内展示施設」も建設中止になりました。そのため、町を元気にするための賑わいづくりも進めていきたいと考えています。温泉掘削は費用もかかると思いますが町民の「あったらいいな!」を実現させるため、私は検討してみる価値はあると考えています。 - 各公民館や町民会館など、町内の公共施設の老朽化に伴い、将来の人口減少を見据えた施設のあり方を検討するなど、誰もが利用したくなる公共施設の整備を目指します。
★芦屋町の人口は減少傾向で、少しでも歯止めをかけられるよう効果的な施策が求められています。しかし、この問題は多くの自治体が抱える問題であって、町特有の問題ではありません。つまり、人口が減るから「ダメ」ではなく、人口が減少しても安心して暮らせる町に変えていくことこそが重要です。
そこで将来を見据え、財源のある間に、まずは老朽化した公共施設の今後のあり方を町のグランドデザインを描き直すつもりで具体的に検討したいと考えています。全ての人がここに行けば誰かに会える、話しができる、笑顔になれる、そんな誰もが利用したくなる公共施設の整備を目指します。 - 買い物しやすい環境の整備やデマンド交通の実証実験を行います。
★買い物に困らない、生活しやすい環境を目指すため、創業支援事業の見直しなどを行います。また、芦屋町の一番の課題は公共交通の不便さです。高齢になっても安心して外出できるようデマンド交通の実証実験を行います。
※デマンド交通とは、利用者の予約に応じて運行される公共交通サービスのことです。 - 農業・漁業・商工業者が元気で稼げるよう支援します。
★農業・漁業・商工業者とともに知恵を出し合い稼げる産業を目指します。
- 芦屋港、マリンテラス、芦屋釜の里、洞山周辺を観光拠点として発展させます。
★芦屋町は、国指定重要文化財「芦屋釜」や響灘の美しい海岸線といった資源を有しています。この海の恵みを武器に他自治体との差別化を図り、今後の観光振興、そして移住・定住促進政策としても展開させます。
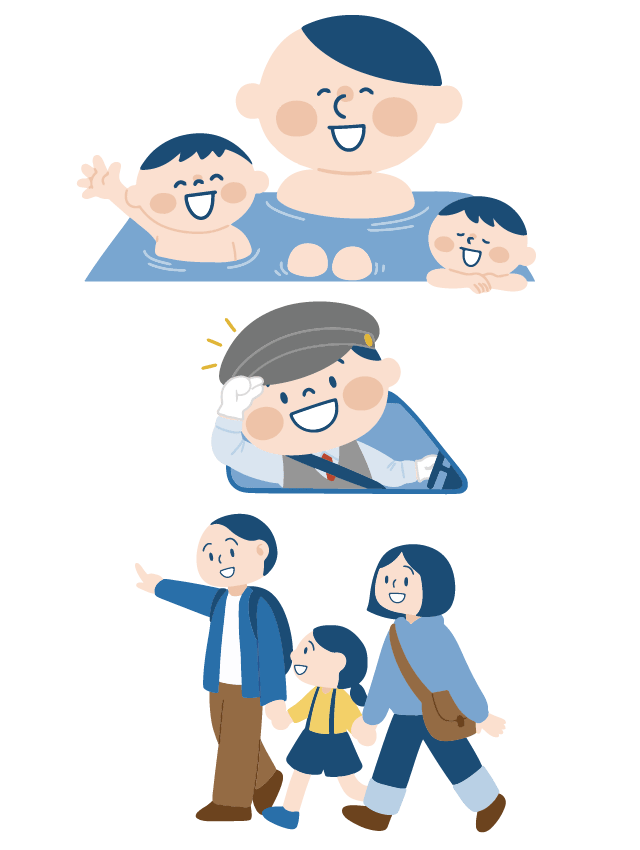
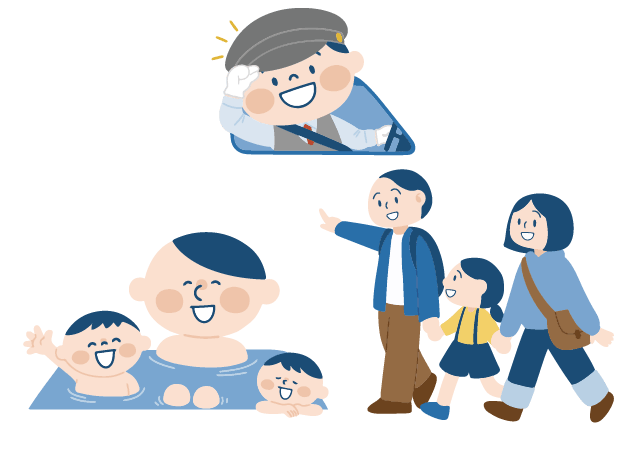
他にも段階的に、以下の取り組みを進めます。
- ごみステーションのごみ収集ボックスの購入助成を行います。
- 認知症の早期発見のため「物忘れ検診」を実施し、その後のフォロー体制を整えます。
- 飼い主のいない猫(野良猫)の取り組みを進めます。
- 運転免許証の返納後の移動手段としてシニアカー(電動車いす)の購入費を助成します。
- 町営住宅の建て替えも含め、移住定住を目的とした住宅政策にも取り組んでいきます。